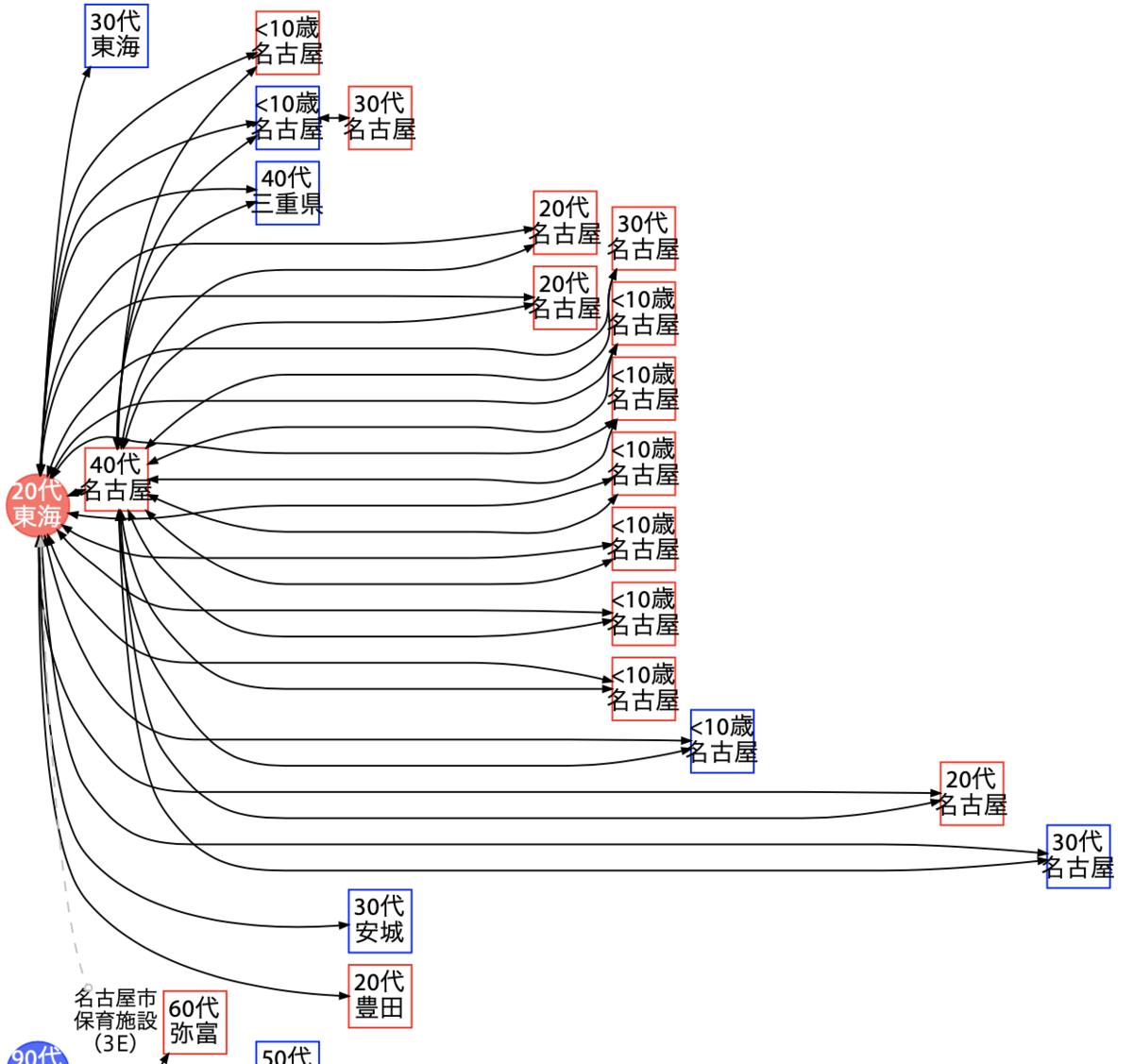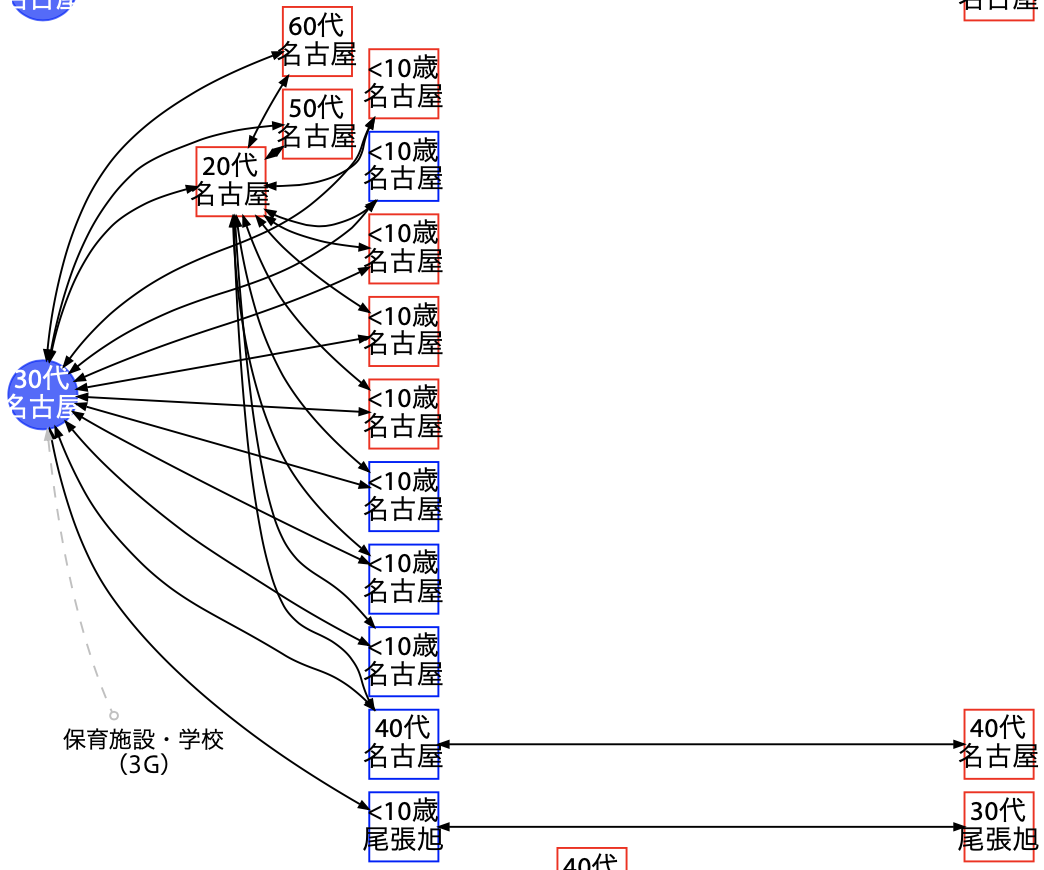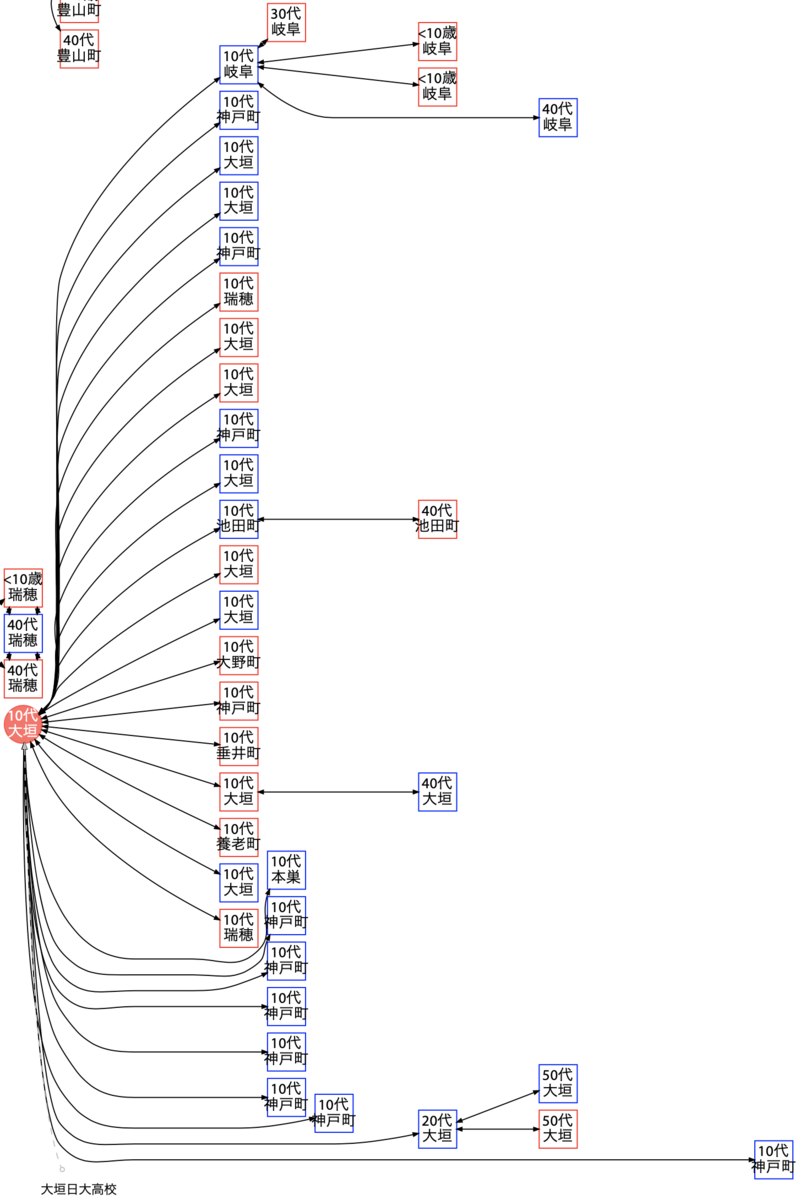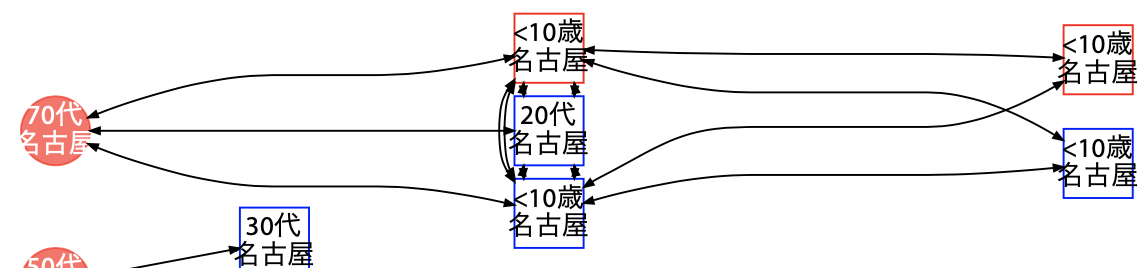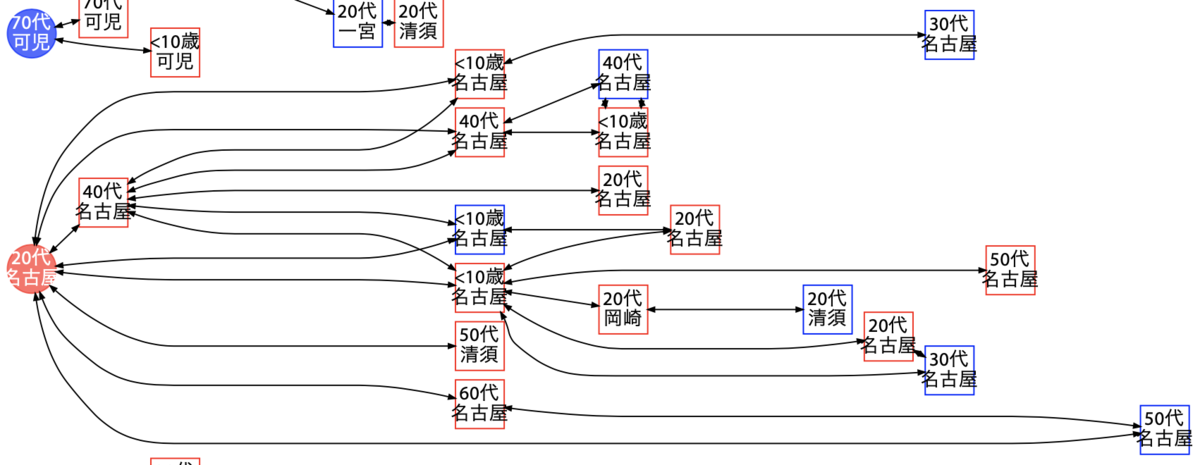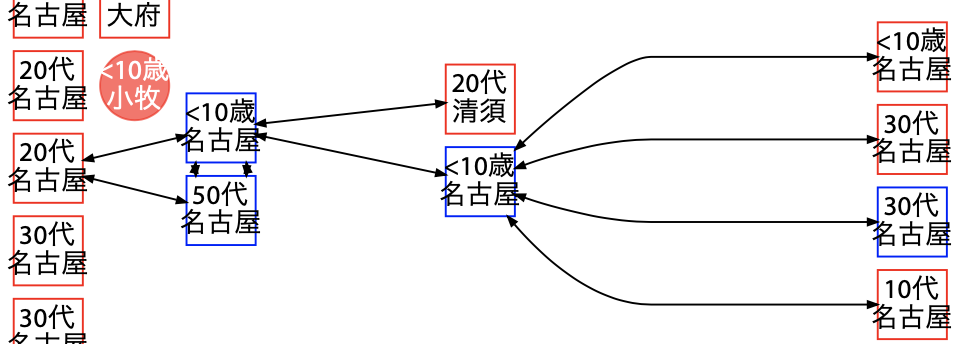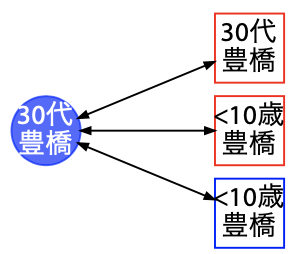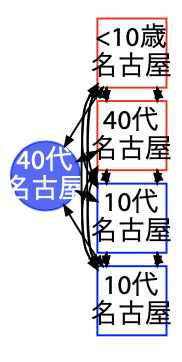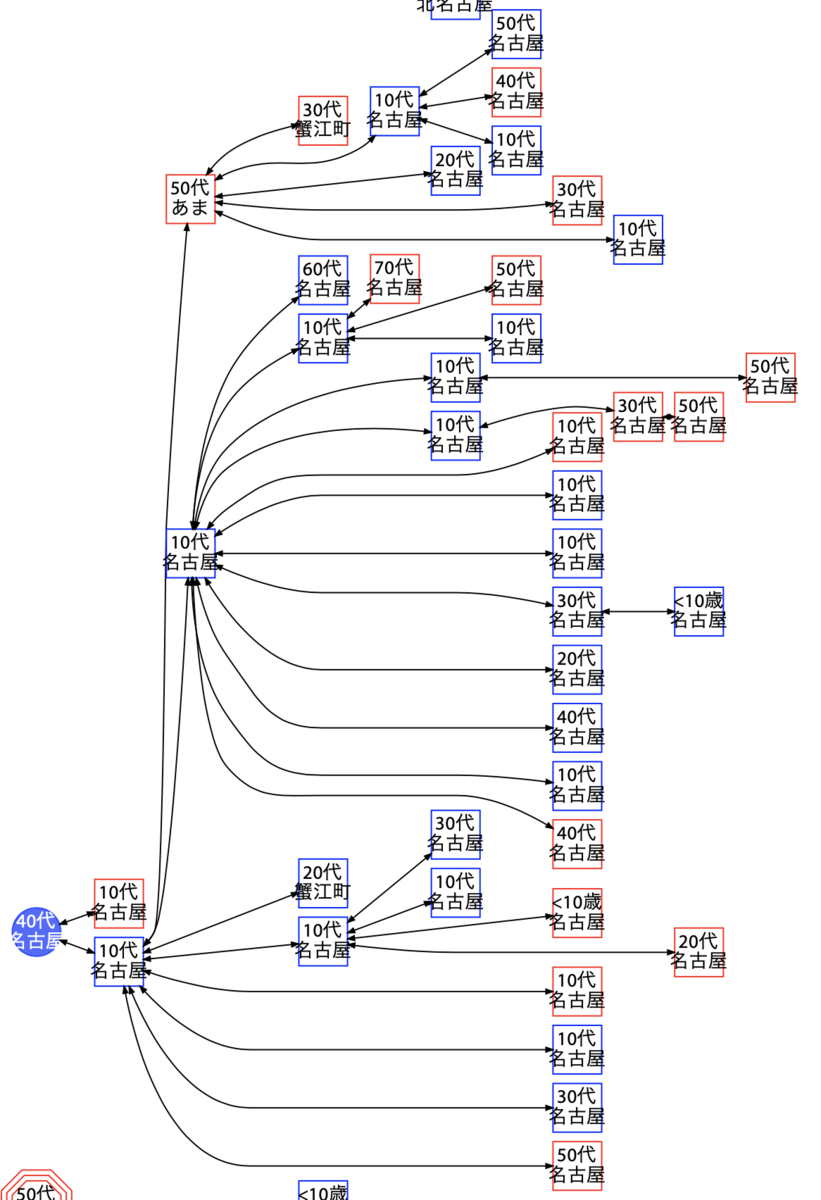LINE 等のやり取りに慣れた最近の学生は、昔からある電子メールに、逆に馴染みがないという場合が増えました。どのような場合に電子メールを使えば良いか、またどのように書けばいいかが入進学の時点で分からないと思いますので、まとめます。
1. なぜ電子メールを使うのか
- 大学ではほぼ全員が使っているから
- 通信プロトコルが公開されているため、特定の企業に独占されないから(LINE/Slack/Teams/WhatsApp/Discord/Messenger/Messages などは互いにやり取りが出来ない)
- 大学などに所属している限り、通常は十分な大きさのメールボックスが与えられため、特定のソフトウェアの有料プランに入らなくても、過去のやり取りやデータをほぼ制限なく保存できるから
- メールサーバー上だけでなく、データ保存が自分の使う計算機上でも行われるため、データ消滅の可能性が低いから
- 複数のアカウントもしくはエイリアスを作ることができ、用途に応じて使い分けられるから
- 1 名から数千名(会ったこともない人)相手に同時に情報を送ることができるから
- 研究者相手であれば、連絡先の電子メールアドレスが公開されているのでいちいち連絡先を交換しなくて良いから
- 大学で与えられるメールアドレスは ac.jp ドメインで終わることが多く、公的な身元を保証しやすいから
- 逆に LINE などの私的な情報を他人に教えなくて良いから
- 多くのメールクライアントでは、メールの返信ごとに自動的にスレッドが作られ、またメッセージに件名を使用することが普通であるため、「あのやり取りどこに行ったっけ?」という事態が起きにくいから
- 単体のメッセージに添付ファイルを多数つけられるから
2. 電子メールの不便な点
3. 電子メール関係の用語
- 件名(Subject):電子メールのメッセージごとにつける題。
- 本文(Body):メッセージの中身の文章部分のこと。
- 添付ファイル:本文とは別に、メッセージに含まれるファイルのこと。
- To:電子メールの送信先アドレスのこと(つまり相手)。
- From:電子メールの送信元アドレスのこと(つまり自分)。
- Carbon Copy(Cc):To 以外に含める送信先アドレスで、同一のメッセージが To にも Cc にも同時送信される。
- Blind Carbon Copy(Bcc):Cc と同様だが、To や Cc の人には Bcc の宛先は表示されない(つまり秘密裏に同内容を他の人に送れる)。
- Reply-To:返信先に使われるメールアドレス。送信元アドレスと一致していない場合がある。例えばメーリングリストに届いたメッセージに返信しようとすると、送信者ではなくメーリングリストに返信して、私的な情報を 1000 人に送りつけるなどの「誤爆」があるので注意。
- メーリングリスト(Mailing List、ML):特定のメールアドレスに送ると、そこに登録している複数人にメッセージが同時送信される。
- 署名(Signature):本文末尾につける、メッセージ送信者の氏名、所属、連絡先などを記した数行の文。
- 返信(Reply):メッセージを送った相手に新たなメッセージを返信すること。このとき元の件名が「レポート提出について」であれば、返信の件名は自動的に「Re: レポート提出について」となることが多い。それ以降の返信も「Re:レポート提出について」となる場合が多いが、一部のメールソフトでは「Re: Re: レポート提出について」となる場合もある。
- 引用(Quote):返信時に、元のメッセージの内容を全部もしくは一部を含めること。
- 文字化け:異なる OS 間ではやり取りできない特殊文字を本文中に使い、相手先でその文字が読めなくなること。
- メールクライアント(Mail Client):電子メールの送受信をするためのソフトウェアのこと。Apple Mail、Thunderbird、Microsoft Outlook など。
4. 電子メールの書き方(全般的な注意)
4.1 件名をつける
新規にメッセージを作成する場合、必ず本文を一言で表す件名をつけてください。「お願い」のように、何のお願いなのか分からない件名は控えましょう。また空欄のまま送信するのも絶対にやめてください。
また、日付などが入っていると親切な場合があります。ただし何十文字も詳しく書きすぎると、相手先で一部非表示になる場合があるため、短くまとめましょう。
大急ぎで返信が欲しい場合には、「【至急】」などを先頭につける場合があります。ただし、目上の人に使ったり、自分がお願いする立場の場合は失礼と取られる場合があるので気をつけてください。
例:
- 「期末試験日程の確認」
- 「XX 研究会の開催について(5/28)」
- 「【至急】履修登録の最終確認(6/5 締切)」
4.2 宛名をつける
電子メールは To 欄にメールアドレスさえ入力すれば、その人にメッセージが届きます。ただし、複数人が To や Cc に入っている場合、誰を主たる対象読者として想定しているのかが分かりづらい場合がありますので、宛名を書き出しにつけるようにしましょう。宛名を読んだときに自分の名前が書かれていたり、また該当する宛名であると感じると、相手もちゃんと読むようになります。
例:
- 「XX 先生」
- 「YY 様」
- 「理学系教員の皆様」
- 「AA 株式会社 ZZ 様」
- 「AA 株式会社御中」(どの部署が適切か分からない場合)
- 「AA 株式会社 営業ご担当者様」(担当者名が分からない場合)
- 「XX 様、Cc YY 様」(XX さんを To、YY さんを Cc に入れる場合)
4.3 名乗る
特に近い関係(友人同士、研究室内)の場合を除いて、宛名の直後に名乗るようにしましょう。誰から届いたメッセージか分からないと、本文を読んでも文脈を掴めない場合があるからです。学生と科目担当教員のやり取りであれば学籍番号を、学内同士のやり取りであれば研究室名を、大学外とのやり取りであれば大学名をつけることが多いと思います。
例:
- 「物理実験学を履修している学籍番号 06234298 の奥村曉です。」(同じ姓の人がいる可能性があるので下の名前も)
- 「CR 研の奥村です。」
- 「宇宙地球環境研究所の奥村です。」
- 「名古屋大学の奥村です。」
4.4 本文
できる限り用件を先に書くようにしましょう。長い文章は誰も読みたくなく、また用件がどこに書かれているか探す作業もしたくないからです。詳細な説明を書く必要がある場合もありますが、それはできる限り後ろに回しましょう。
また、報告なのか、相談なのか、質問なのか、お願いなのか、一体なんだか分からない文章を書くのはやめましょう。複数の質問がある場合は、例えば「XX について 2 点質問させてください」のように、いくつあるのか明示するのも効果的です。
4.5 使用する文字
4.6 返信をする
LINE で「既読」と表示されるような機能が、電子メールにはありません(あるにはあるのですが、一般的に使用されていません)。また多数のメッセージに埋もれてしまい読み落とすということもありますので、それで逆に相手の手を煩わせない限り、メールを読んだ、指示を理解した、対応に感謝している、などを相手に伝えましょう。
5. 電子メールの書き方の例
5.1 学生から講義関係で大学教員に送る場合
大学教員は毎年多数の学生とやり取りするため、名乗ってもらわないと、また学籍番号を記載してもらわないと成績に反映させる作業が非常に面倒です。また教員は多数の電子メールを処理するため、メールの本文で意図の読みきれないものや、件名の書かれていないものは対応しきれません。
- 必ず件名をつけること
- 氏名と学籍番号を書くこと
- 用件が何かを明確にすること(最悪の例「レポートが間に合いそうにないのですが。」)
- 「奥村様」でも「奥村先生」でも「奥村さん」でも、物理系はなんでもいい。分野によっては「さん」や「様」で怒る人がいるので注意。雰囲気がよく分からなければ「先生」が無難。
- 「お世話になっております」や「お忙しいところ失礼します」は物理系は不要。特に前者は「お世話しているつもりはない」と感じる。お願いごとをするときなどは、後者はあっても良い。
例:
件名:課題提出締切の延長のお願い
奥村先生
物理実験学を履修している学籍番号 XXXX の名大太郎です。
6/10 提出締め切りの課題ですが、身内に不幸があったため現時点で提出できる見込みがありません。私的な理由で申し訳ございませんが、もしで可能であれば締め切りを 6/14 に伸ばしていただけないでしょうか。
名大太郎
この例文だともっと色々と追加したい人もいるかもしれませんが、メールが丁寧かどうかでこの手の教員側の判断は変わりませんので、失礼でさえなければ十分だと思います(自分が受信する立場であれば)。
5.2 学生から研究室訪問の依頼を大学教員に送る場合
普通の研究室は、研究室訪問を随時受け付けています。またメールアドレスを公開しているということは、メッセージを送りつけて良いということです。
- 教員は忙しいので時間調整がすぐにできることを期待しないこと
- 教員は返信し忘れる場合があるので、返信がなければ再送しても失礼ではない
- それでも返信がない、もしくはある程度の礼節を弁えたと自分で思っているメッセージに憤慨するような教員であれば、そんな研究室は行かない方が良い
- その研究室を訪問するにあたり、何に興味があるのかを先に伝えておくと良い(その研究をやっている院生の時間調整をしたりもしてくれる)
- 訪問可能な日程を複数提示し、そこから選んでもらうとやり取りが短く済む(ただしそれで怒る人もいるらしい)
- 名乗る(特に他大学の場合は、所属研究室がどこかも伝えると話が弾みやすい)
例:
件名:研究室訪問のお願い(東大:名大太郎)
奥村先生
東京大学物理学科 4 年の名大太郎です。CR 研究室での研究に興味を持ち、研究室訪問ができないかと思いメールをお送りします。
現在は東京大学の XX 研究室で YY の卒研を行なっているのですが、大学院からは ZZ やその周辺分野の研究をしたいと考えています。名古屋大学の大学院受験にあたり、事前の研究室訪問と、もし可能であれば大学院生の方ともお話しできればと思います。
こちらからの日程の提示になり恐縮ですが、以下の候補であれば講義がないため研究室にお伺いすることが可能です。ご多忙とは存じますが、もし以下日程候補で可能なものがあれば、お知らせいただけないでしょうか。
候補 1:…
候補 2:…
候補 3:…もし上記日程で難しい場合、ご都合の良い日程をご教示いただけると大変助かります。
名大太郎
これも人によってはもっと書くことがあるかもしれませんが、まあこれで十分だと思います。
5.3 研究関係のやり取り
既知の学生同士、もしくは研究者相手の議論などの場合、論点をはっきりさせることが重要です。
- 箇条書きを効果的に使うこと
- 長文になる場合、本文に構造を持たせて可読性を高めること
- 用件が何なのかをはっきりさせること
- 議論や報告と質問を切り分けて書くこと
例:
件名:測定結果の報告と質問
奥村様
名大太郎です。先日議論させていただいた測定の結果が出ましたので、その報告と、実験結果の解釈について 3 点質問があります。報告資料は添付ファイルの通りです。
■ 実験結果
□ 線形性の測定
添付スライド 1 ページ目にある通り、…□ 時間安定性の評価
…■ 質問
Q1. 3 ページ目の測定を見ると、先行研究と違う結果が得られました。これは…
Q2. …
Q3. …
以上、よろしくお願いいたします。
名大太郎
6. Cc と Bcc の使い方
基本的にはメッセージ送信時に相手のメールアドレスを To 欄に入れます。ただし、本文をちゃんと読んでもらう必要はないが、記録として他の人にも同時送信しておきたい場合があります。この時に使用するのが Cc 欄です。
例:
- 研究費の使用許可と財源の指定を既に指導教員から口頭で貰っており、大学事務と学生とのやり取りで指導教員を Cc に入れる。
- ゼミの連絡を回す際に、毎回出席すると宣言している修士学生には To 欄を使い、時間があれば出ると言っている博士学生は Cc に入れる。
- 他大学の共同研究者や企業とやり取りするとき、指導教員を Cc に入れる。
Cc の使用は、自分を守るためにも使えると思っておいてください。「聞いていない」に対して、「ちゃんと Cc しましたよね」と言い返すことができます。
また Bcc は使いどころが分からないかもしれませんが、同じ情報を他の人に伝えつつ、その行為を秘密にしたい場合、もしくは宛先を秘匿したい場合に使います。
例:
- ハラスメントの加害者に注意をするとき、被害者を Bcc に入れる。
- なんらかの苦情を A と B の 2 名から C に送るとき、A と B が連携していないかのように C に見せるため、A と B は互いに Bcc を使う。
- メールアドレスを互いに知らない複数の相手に対して、一斉に同内容のメッセージを送る。例えば研究会の連絡を参加者全員に通知する場合。これは個人のメールアドレスという情報を、他人に勝手に漏らさないという原則に基づく。
ただし、From: A → To: B、Cc: C、Bcc: D で送信した場合、B や C は D に送信しているということが一切分かりませんので、B や C が A に対して返信を行うと、D にはその返信が届きません。
7. その他の細かい注意点
- 何時に送信しようが「夜分遅くに失礼します。」は不要。寝ている時間に受信音が鳴る設定になっているのであれば、それは受信側の問題であって、送信側は気にする必要はない。また送受信の際に世界中のどこにいるかも知ったことではない。
- 添付ファイルはせいぜい合計 5 MB 程度に抑える。大きくなる場合、外部サービス(Dropbox や Google Drive など)を使ってアップロードし、そのリンクを送る。
- Cc に入っている人も含め、原則は全員に返信をする。元のメールは何らかの意図が Cc を使用している。「返信(Reply)」ではなく、「全員に返信(Reply All)」の機能をいつも使う癖をつける。前者は送信者にしか返信せず、後者は他の To や Cc の全員を含めて返信する。
- 「Teams のファイルのところにアップロードしました」などではなく、ちゃんとリンクを貼り付ける。
- 使用しているメールクライアントで送信者名を設定する。これをしないと、送信元が電子メールアドレスのみの表示となり、誰から届いたのか分からない。
- 誰かに新規用件でメール送信をする場合、過去のやり取りに返信する形でメッセージ作成をしない。この場合、件名を変更してもメールクライアントが同一スレッドにまとめてしまう(ヘッダーにどのメッセージに返信したかの情報が書き込まれるため)。
- 件名にだけ用件を書き、本文には「表題の件について」とだけ書くことを避ける。読み手は件名を読み返さないといけなくなる。(これは名大の事務の謎文化で本当にやめてほしい。)